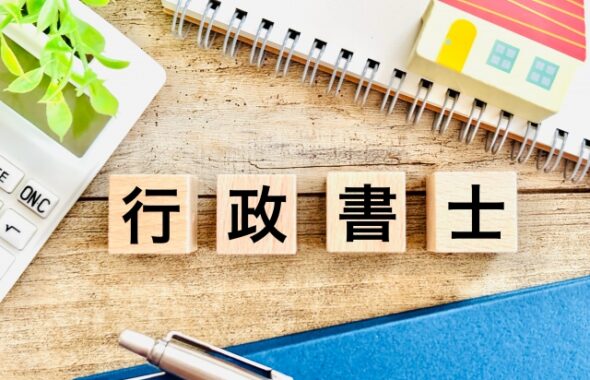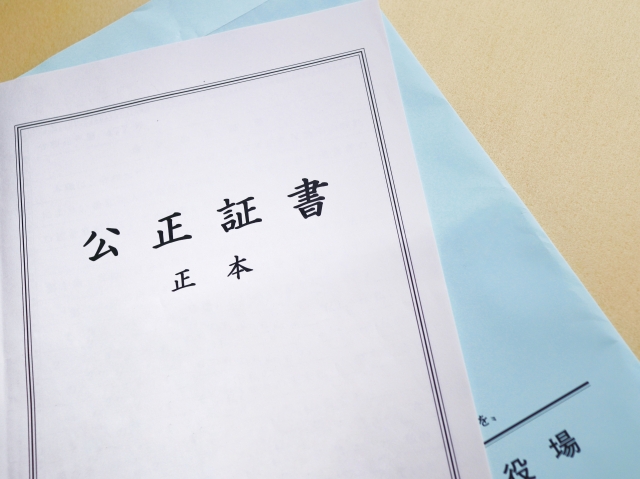
配偶者もおらず、相続させたい人もいませんが、親を交通事故で亡くした子供たちなどに、育英の寄付をしたいと考えています。どのような手続きになりますか
「配偶者もおらず、相続させたい人もいませんが、親を交通事故で亡くした子供たちなどに、育英の寄付をしたいと考えています」
このようなご相談を先日いただきました。
人生の最期に、自分の財産を社会や誰かの役に立てれれば‥そんな心のこもった想いをどのように実現できるのか。
今回は「相続させたい人がいない…”育英の寄付” として残すには?」についてご紹介します。
▶ 遺言がない場合は、財産は国のものになる
まず初めに、知っておきたいこととして、遺言書がない場合、亡くなった後の財産は法律に則って相続されます。
これが、配偶者や子、親、兄弟姉妹の相続人が誰もいない場合は、最終的にその財産は国庫に帰属します。つまり、財産は国のものとなるということです。
せっかくの想いがあっても、何も対処していなければ実現される可能性はゼロに等しくなります。
▶ 寄付したい場合は遺言で「遺贈」を指定する
財産を特定の団体や目的として活用してもらい場合、遺言書でその意志を明確にしておきましょう。これは ”遺贈(いぞう)” という方法です。
遺贈には、大きく分けて2つのパターンがあります。
- 包括遺贈(ほうかつ・いぞう):財産の全て または 割合を指定して寄付を行うこと。(例:全財産の50% など)
- 特定遺贈(とくてい・いぞう):具体的な財産を指定し、寄付を行うこと。(例:○○銀行の預金100万円 など)
寄付先として選ばれるのは、多くの場合、公益法人や認定NPO法人です。
例えば、「交通遺児育英会」「あしなが育英会」など、代表的なの団体が挙げられますが、全国には遺児支援に取り組む団体がいくつか存在しています。
団体によって、理念や遺贈の受け入れ体制が異なります。名称だけで判断せず、公式サイトや報告書を参考にしながら、”自分の想い” と団体の支援内容が合っているかをよく調べて、遺贈先を考えていきましょう。
▶ 確実に意志を遺せる「公正証書遺言」
遺言書にはいくつかの形式がありますが、今回のご相談内容には最も確実でトラブルの少ない「公正証書遺言」がおすすめです。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう方法で、
✅偽造や紛失の心配がない
✅家庭裁判所の検認が不要 といった特徴があります。
▶ 寄付を受け入れる団体にも事前に相談を
遺贈を実際に検討される場合は、寄付先として想定している団体にも事前に相談するのがおすすめです。
一部の団体では、
- 遺贈方法や使途(奨学金や施設支援 など)を指定できる
- 寄付者の名前を記録として残せる制度 などを設けていることもあります。
また、団体によっては、相続税の非課税対象として扱われることもあります。
▶ 遺贈手続きの流れ
最後に、育英寄付などの遺贈手続きの流れを簡潔にお伝えします。
- 遺贈先(寄付先)の団体を決める:団体によって受け入れ体制や手続きが異なる。
- 遺言書の作成:公正証書遺言が一般的かつ、法的効力があり確実。
- 遺言執行者を指定:遺贈を実際に執行してくれる信頼できる人や専門家をしてすると◎
- 事前に団体へ相談:寄付の使い道や受け入れ方針を確認しておくと安心。
- 財産目録の整理と書類の保管:寄付対象となる財産を明確にすること。遺言書の保管場所を専門家や信頼できる人に伝える。
▶ まとめ[想いを ”形” として残すために]
「自分の財産を誰かを支えるきっかけに‥」
その想いを実現させるには、生前での準備がとても大切です。
相続や遺言となると、重く難しく感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そう感じたら、あなたのこれまで築かれてきた財産や想いを、次世代に託すと考えてみてください。
行動することは、少し勇気のいることかもしれません。でも、その勇気が誰かにとっての道しるべになることもあります。
遺贈や寄付についての手続きについてのご相談も承っております。
種と実 行政書士事務所は、あなたの想いを形にするお手伝いをいたします。些細なことでも、まずはご相談ください。
種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。
大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。