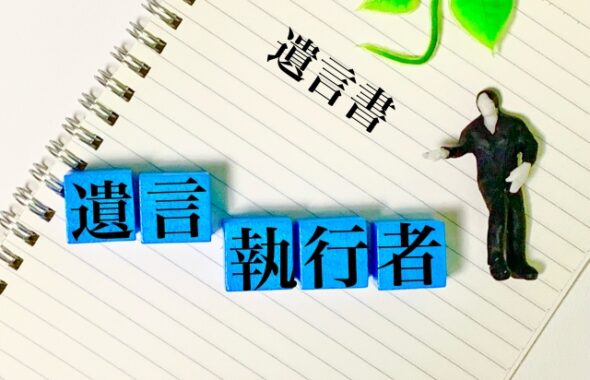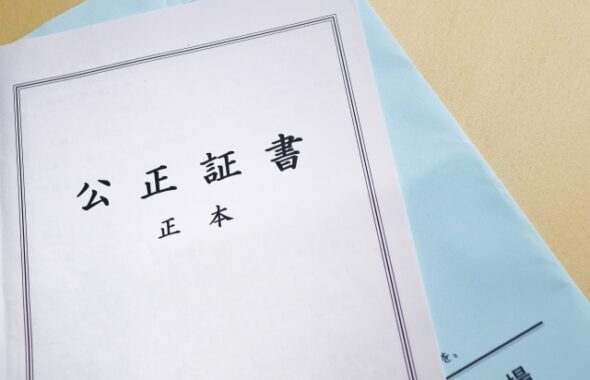遺言書には「秘密証書遺言」というのがあると聞きました。どんなものでメリットやデメリットも教えてください。
遺言書にはいくつかの種類があります。
これらの遺言書にはそれぞれに特徴、メリットとデメリットがあり、作成する遺言者の考え方や状況によって遺言方法の検討が必要となります。
そこで今回は「秘密証書遺言」についてご紹介します。
▶ 秘密証書遺言とは
内容を秘密にしつつ、遺言の存在自体を公証役場で認証してもらう遺言書のことを言います。
遺言者が自ら作成し、封筒に入れ、封印をした上で、公証人と証人2名の前で「これは自分の遺言書である」と宣言し、公証人に認証してもらいます。
*公証人は遺言内容の確認は行いません。
▶ 秘密証書遺言のメリットとデメリット
[メリット]
- 遺言内容を秘密にできる:公証人や証人に遺言内容を知られることがないので、プライバシーを守ることができる。
- 偽造・改ざんのリスクが低い:公証役場で認証を受けるため、遺言の存在自体が公的に証明され、偽造・変造のリスクを減らすことができる。
- 自筆証書遺言よりも自由度が高い:遺言の本文は自筆でなくてもOK(パソコン・代筆も可)。但し、遺言者の自筆署名は必要。
[デメリット]
- 遺言内容が無効になる可能性がある:公証人が遺言内容を確認しないため、法律上の要件を満たしていない場合は無効になる可能性がある。
- 家庭裁判所での検認が必要:自筆証書遺言と同様、相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要。これによって相続の手続きが遅れる可能性がある。
- 公証役場での手続きが必要:公証人と証人2名の立ち合いが必要になるため、時間と手間がかかる。
▶ 秘密証書遺言の作成手順
1.遺言書の作成
- 自筆・パソコン・代筆のいずれかで作成を行う。但し、遺言者の自筆署名は必要。
- 用紙やフォーマットは自由。但し、法律の要件を満たさなければなりません。
2.遺言書を封筒に入れて封印
- 遺言書が書き終わったら、封筒に入れて封をする。(*封筒の上にも署名が必要。)
3.公証役場で手続きをする
- 遺言者本人、公証人、証人2名(知人・行政書士・司法書士など)と共に公証役場で手続きをする。
4.遺言を公証人に証明してもらう
- 遺言者が「これは自分の遺言書である」と宣言し、公証人が確認、証人と共に認証手続きを行う。
5.遺言者が遺言書を持ち帰る
- 遺言書は公証役場では保管せず、遺言者本人が保管する。この時、遺言書を失くさないように注意が必要です。
▶ 秘密証書遺言に向いている人
以下に該当される方は、「秘密証書遺言」の作成がおすすめです。
- 遺言内容を誰にも知られたくない人
- 公証人に内容をチェックされたくない、プライバシーを重視したい人
- 自筆証書遺言では不安、でも公正証書遺言ほどの手間をかけたくない人
一方で、遺言内容を確実に執行されるのを重視する人は、「公正証書遺言」がおすすめです。
▶ 他遺言方法との比較
以下、秘密証書遺言と他遺言方法との比較です。
| 秘密証書遺言 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作成の手軽さ | △(公証役場で認証が必要) | ◎(自分だけでOK) | ×(公証人と証人2名が必要) |
| 内容の秘密性 | ◎(公証人・証人にも秘密) | △(遺言内容を見られる可能性あり) | ×(公証人が内容を確認) |
| 偽造・改ざんリスク | ○(認証はあるが、保管は自己責任) | △(紛失・改ざんのリスクあり) | ◎(公証役場が保管する) |
| 法的な確実性 | △(要件不備の可能性あり) | △(要件不備で無効のリスクあり) | ◎(公証人が作成する) |
| 検認の必要性 | 必要 | 必要 | 不要 |
▶ まとめ
遺言内容を秘密にでき、遺言の存在を公証役場で認証してもらうの方法が「秘密証書遺言」でした。
自筆でなく、パソコンや代筆が可能など、作成に自由度が高いのが魅力な反面、公証人の確認がないため、法律上の要件を満たしていない場合は無効になる可能性があります。
遺言内容を確実に執行されることを重視したいのであれば、手間はかかりますが、公正証書遺言がおすすめです。
状況や考え方は人それぞれ。自分にあった方法を選ぶことが大切です。
種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。
大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。