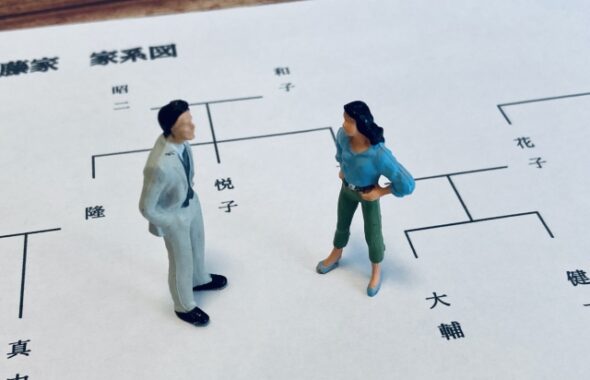遺言執行者について、誰がなるのがいいのか教えてください。相続人は、妻と子ども2人です。妻は認知症が進んでいます。
遺言内容を正しく実現するには遺言執行者(いごんしっこうしゃ)の選任がとても重要です。
ご家族の関係性や、健康状態によって、執行人の選出方法も異なります。
今回は、相続人は妻と子ども2人。妻は認知症が進んでいるというケースをもとに「遺言執行者の選出方法」についてご紹介します。
▶ 遺言執行者とは
遺言書を書いた人(遺言者)が亡くなった後、その遺志を正しい形で実現するには、様々な手続きが必要です。
その遺言内容を実際に、実行する人のことを遺言執行者(いごんしっこうしゃ)と言います。
例えば、「誰に何を相続させたいのか」「認知をする」など、遺言で指示されたことを相続人に代わって手続きを行う立場です。
簡単に言い換えれば、[亡くなった人(遺言者)の代理人]として遺言書の内容を執行する人です。
遺言書が公正証書で作られていた場合でも、遺言内容を実行するには法的な手続きや相続人との調整が必要不可欠なため、執行者の存在はとても重要と言えます。
▶ 遺言執行者がいない場合どうなるのか
遺言に執行者の指定がされていない場合、家庭裁判所を通じて選任してもらうことが可能です。
ただし、その場合は手間や時間がかかるため、相続人同士の意見が分かれるケースでは、相続の話し合いが進まないことも考えられます。
遺言書が作成の段階で「誰に執行してもらうのか」を明確にしておきましょう。
▶ ご相談者さまのケースで気を付けたいこと
今回のような「妻と子ども2人が相続人で、妻は認知症が進んでいる」というケースでは、以下のことに気を付けましょう。
1.認知症の妻は執行者にはなれない
遺言執行人は、一定の法律行為を行う責任のある立場です。
認知症が進んでおり、判断能力が不十分な方は執行人として選任することができません。
従って、このケースでは奥さまに遺言執行人をお任せすることはできないのです。
2.子どもを執行者にする場合
お子さまの1人を執行者にすることは可能です。
しかし、人というものは、いくら法律があっても、気持ちの面で割り切ることは簡単ではありません。
他の相続人との関係性によってはトラブルの火種になることもあります。
例えば、長男(長女)が全てを取り仕切ることに次男(次女)などの兄弟が不満に感じることも考えられます。
これまで良好な家族関係であっても、相続に関する対立は今後の関係性に影響を及ぼすこともあります。トラブルなく、公平な執行を望むのであれば、専門家や第三者への依頼も選択肢として入れておきましょう。
3.専門家を執行者にするメリット
行政書士や弁護士などの専門家を執行人に依頼するメリットは以下の通りです。
- 専門的な知識で手続きを代行してくれる
- 中立的な立場で公平に執行してくれる
- 相続人の不安が軽減できる
- 円滑な相続を支援してくれる
相続財産が多い場合や、今回のケースのように相続人の中に認知症の方が関与している場合、専門的な判断が必要になることも。
その場合、専門家へ依頼することでスムーズな対応が期待できます。
▶ まとめ
遺言執行者は、遺言内容を実行するとても重要な存在です。
法的な手続きや相続人との調整がを行うなど、判断能力は必要不可欠です。
今回のご相談者のようにご家族に認知症の方がいらっしゃる場合、その方は遺言執行人を任せることはできません。
また、お子さんがいらっしゃる場合でも、中立的な立場での執行となると、おすすめとは言い切れません。
相続トラブルを防ぐ意味では、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することを選択肢に入れておくと安心です。
種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。
大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。