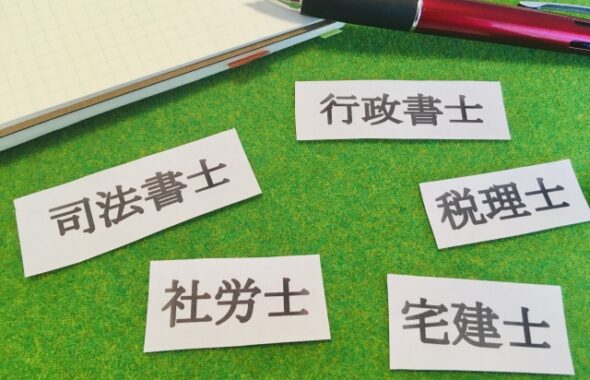終活とは何歳から始めるべきですか?大きくやることリストを教えてください。
生きていれば、最期の時は誰にでも訪れます。最期を迎えるまでをあなたはどのように過ごしますか。
終活は70代80代の方が進めているイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、50代60代の若年層から、終活を始めても問題ありません。
今回は「終活を始める年代とやることリスト」をご紹介します。
▶ 終活開始の適齢期とは
終活を始めるには明確な適齢期はありませんが、一般的には、50代~60代頃から終活を意識し始める方が多くいらっしゃいます。
但し、持病の有無やライフスタイルによって終活開始時期は異なります。
▶ 年代別の終活
年代によって終活の進め方が異なります。以下、年代ごとの終活内容です。
[50代:老後資金の整理や家の片づけを開始が望ましい時期]
体力も気力もまだまだ十分な50代。将来に向けて ”終活を意識し始める大切な時期” です。
<やるべきこと>
✅ライフプランの見直し
- 退職後の生活設計を始める(収入や支出のバランスを確認)
- 老後の住まいをどうするのか(持ち家?住み替え?)
✅財産整理を開始する
- 預貯金や不動産、保険の整理を行う
- 住宅ローンや借入金を改めて把握する
- 現在未活用の銀行口座やクレジットカードの解約
✅生前整理
- 自宅内にある必要ないものを少しずつ処分していく(1日1捨てなど)
- 思い出の品や写真の整理
✅健康維持を意識する
- 定期的な健康診断の受診
- 生活習慣病予防をする(運動や食事の見直し)
✅終活について家族と話し合いを開始
- 今後どう暮らしたいのかなどを伝えておく
- 病気になった時のことを考える
[60代:本格的に終活を進めるのが望ましい時期]
定年退職や年金受給が開始したり環境の変化を感じる60代。人生の後半をどう過ごしていくのか ”自身と向き合う時期” です。
<やるべきこと>
✅エンディングノートを書き始める
- 自分の経歴・財産・趣味・希望などを書き始める
- 介護や医療が必要になった場合の希望(延命治療を希望するか否か)
✅相続対策を始める
- 遺言書の作成(財産分与をどうするのか)
- 相続税対策の相談をする
✅葬儀やお墓について考え始める
- 葬儀の希望を明確にする(家族葬?一般葬?)
- お墓の選択肢を検討する(墓じまい?永代供養?)
✅生前整理を本格的にする
- 物だけでなく、デジタル遺品と言われるSNSやネット銀行などの整理をする
✅介護への備えをする
- 介護保険制度を理解しておく
- 将来の介護施設の選択肢を調べておく
✅身寄りのない方の場合、死後事務委任契約を検討する
[70代:終活を仕上げる時期]
<体力や判断力の衰えを感じ始める70代。早めに手続きを終わらせ、”老後を安心して過ごせるよう、終活の仕上げをする時期” です。
<やるべきこと>
✅遺言書の最終確認
- 50~60代から状況が変わっていれば、遺言内容の見直しがおすすめ
- 公正証書遺言もおすすめ
✅介護や医療の具体的な準備を進める
- 認知症対策を行う(任意後見契約を利用し、認知機能低下した場合に備える)
- 延命治療や尊厳死に対する意識表示をする
✅財産管理を明確にする
- 財産の保管場所を家族に伝えておく
- 銀行や証券口座の整理を進める
✅身の回りの整理完了
- 服や家具などを処分する(本当に必要な物のみを残す)
✅死後の手続きの準備をする
- 葬儀の具体的な手配について事前相談をしておく
[80代:終活の最終確認と終活内容を家族に引き継ぐ時期]
終活の最終仕上げを迎える80代。家族や専門家に ”終活内容を引き継ぐ時期” です。
<やるべきこと>
✅家族への最終確認
- 財産管理や遺言書の確認を行う
- 介護や医療に対する意思の最終決定
✅身の回りの最終整理
- 本当に必要な物のみ残す
- 重要書類を1か所にまとめる
✅死後の準備を家族に具体的に伝える
- 葬儀会社や納骨方法の最終確認
- 供養方法を家族と話し合う
✅デジタル遺品の完全整理
- パスワード管理を家族に伝えるもしくは、削除
▶ まとめ
今回は、年代別で終活内容を紹介しました。
内容と年代はあくまでも、一例です。体調や環境の変化があれば、年齢にこだわらず終活を始めても構いません。
ですが、早めに準備を進めることで、「自身の安心感」と「残されるご家族への負担軽減」というメリットがあります。
終活は、死後に向けて「やらなければならないもの」ではなく、「よりよく生きていくための準備」です。
焦りすぎず、あなたのペースで進めてください。
種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。
大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。