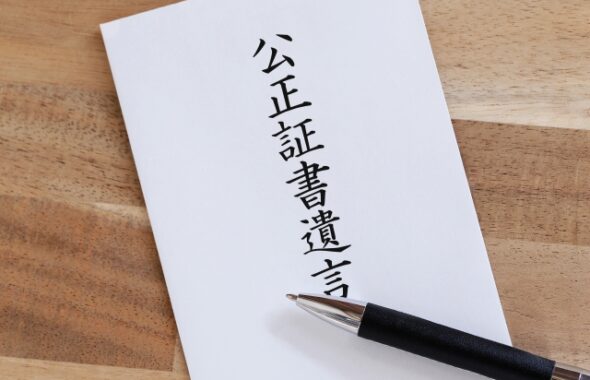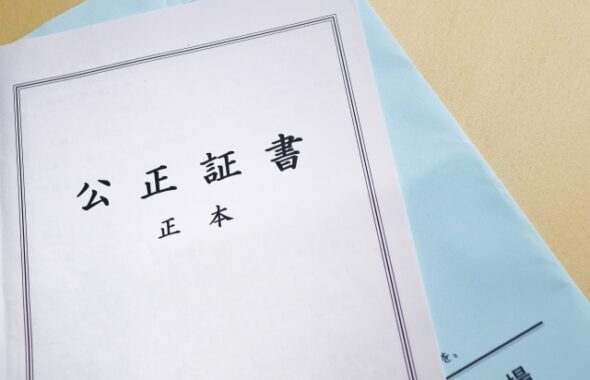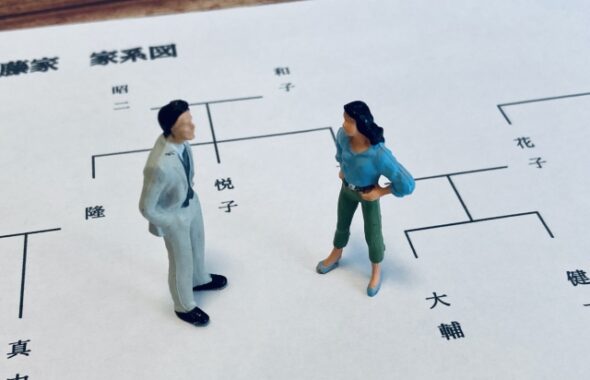生命保険は相続財産になりますか?受け取った死亡保険金に税金がかかるのでしょうか
相続手続きに関する相談の一つに被相続人(亡くなった方)の保険金の扱いについて、よく質問をいただきます。
そこで、今回は「生命保険は相続財産になる?税金はどうなるの?知っておきたい基礎知識」についてご紹介します。
▶ 生命保険は相続財産になる?
結論からお伝えすると、指定された受取人がいる場合、生命保険金は相続財産には含まれません。
その理由は、受取人に「保険契約によって直接権利が移る」ため、民法上の相続財産とは区別されているからです。
例えば、被相続人(亡くなった方)が配偶者や子どもを受取人として指定している場合、その人が直接保険金を受け取る権利を持っています。よって、遺産分割協議の対象外となります。ただし、例外もあります。
▶ 受取人が「指定なし」の場合は?
保険契約書に受取人の欄が「空欄」または「相続人」とだけ記載されていた場合、死亡保険金は法定相続人全員が受け取る権利を持つことになります。
この場合、死亡保険金は相続財産とみなされ、遺産分割の対象になる可能性があります。
▶ 保険金の扱いは受取人の有無
受取人の指定があるかどうかで保険金の扱いは大きく左右されます。
相続トラブルを避けるためにも、生前に受取人の確認や見直しをしておくことがとても重要になります。
▶ 死亡保険金(生命保険)に税金はかかる?
続いて、死亡保険金(生命保険)の税についてご紹介します。保険金には原則、相続税が課税されます。
ただし、保険金には「特別な非課税枠」というものが用意されています。
▶ 特別な非課税枠とは?
相続税法には、計算式によって枠が定められています。
これは、遺族の生活保障という生命保険本来の趣旨を考慮し、一定の金額までは課税しないというルールを意味しています。
非課税枠(非課税限度額)は以下の通りです。
計算式:500万円×法定相続人の数
[例)被相続人に配偶者と子ども2人で、法定相続人が合計3人の場合]
500万円×3名=1,500万円 となります。
法定相続人が3人いれば、上記の「1,500万円」までが保険金の非課税部分で、超過部分が相続税の対象となります。
仮に3人いて、受取人の1人が2,000万円を受け取った場合、1,500万円から超過した500万円が相続税の課税対象です。
(※つまり、非課税なのは、1人当たり500万円が上限!600万円になると課税対象になり、500万円以下は非課税です。)
▶ 生命保険に対する注意点
注意点は以下の通りです。
1.受取人は法定相続人であること
非課税枠の適用は、保険金の受取人が法定相続人に限られます。
法定相続人でない孫や内縁の夫(妻)などは、非課税枠の適用外です。
2.複数人が保険金を受け取った場合
非課税の限度額は相続人全体に対しての上限額です。受取人1人あたりではありません。
3.他財産と合算で計算される
非課税枠を超えた保険金は、他の遺産(預貯金や不動産)と合算し、相続税が計算されます。
4.組み合わせで税が異なる
生命保険は、組み合わせ(契約者・被保険者・受取人)によってかかる税金が変わります。
被保険者と契約者が同じで、受取人が法定相続人:相続税
契約者と受取人が同じで、被保険者が別の人物:所得税(一時所得)
契約者と被保険者が親で、受取人が子ども:贈与税
保険加時や見直しのタイミングに専門家への確認が大切です。
▶ まとめ
生命保険は、受取人が指定されていれば、受取人が保険金を受け取る権利を持っています。
この場合、保険金は相続財産には含まれません。受取人の指定がない場合は、法定相続人全員が受け取る権利を持つことになり、遺産分割の対象になる可能性があります。
また、本来であれば、相続税の課税対象となる保険金ですが、金額によって「特別な非課税枠」が設けられており、一定の金額までは非課税される特別なルールも存在します。
しかし、組み合わせ(契約者・被保険者・受取人)によって、税金の種類が異なるため、特別ルールが適用されないこともあります。
保険を契約される方、見直しをお考えの方は、一度専門家にご相談されることをおすすめします。
種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。
大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。