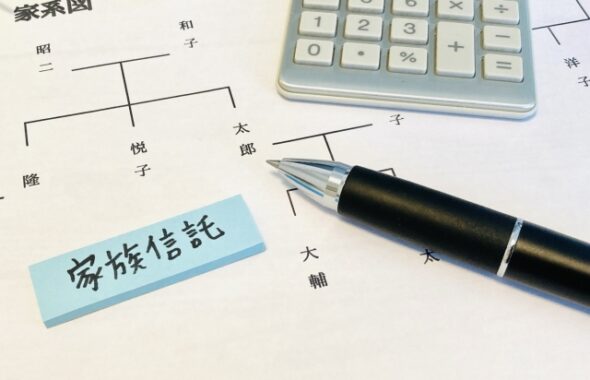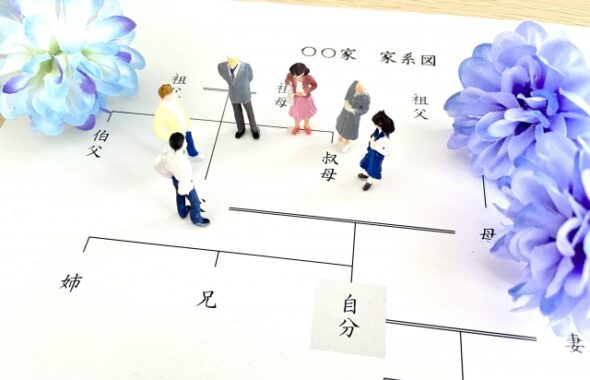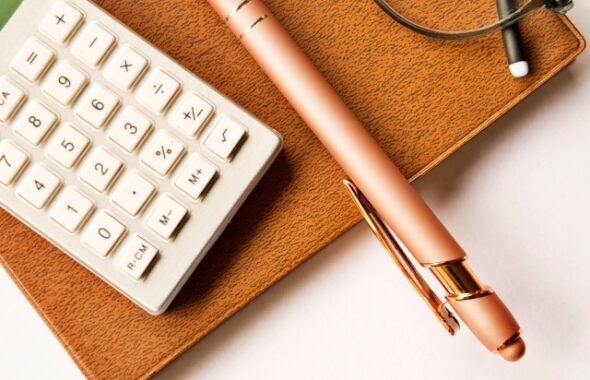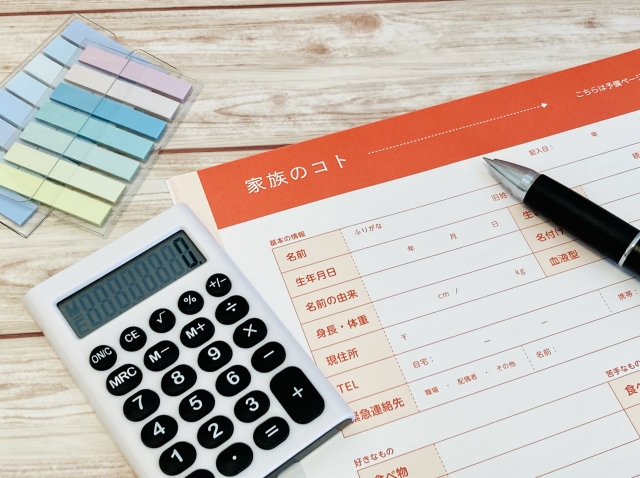
生前整理を始めることで、どのように費用を抑え、将来的な安心を得られますか?なにからどう始めればいいのでしょうか
先のことは誰にもわからないように、最期はいつ訪れるのかはわかりません。
わからないからこそ、今できることを進めておくことが、これからの安心に繋がります。その、今できることの1つに ”生前整理” があります。
生前整理は、あなたの身の回りのもの(品物・財産・あなたの将来への意志)を整理するもの。
始めるといっても、何から手を付けていけばいいのかわからないこともあるかもしれません。
今回は「生前整理は何から始める?始めることで費用削減なるのか」についてご紹介します。
▶ 生前整理のメリット
まず、生前整理を始めるメリットは以下の通りです。
1.費用の削減ができる
- 無くなった後の遺品整理を業者に依頼すると高額になることが多い。(数十万円~百万円以上かかることも)
- 不要な物を事前に整理することで、財産相続をシンプルにでき、不用品の処分費用を抑えられる。
2.トラブルの回避
- 財産分配を明確にしておくと相続時の争いを防ぐことができる。
3.安心感を得ることができる
本人の希望に沿った形で整理が進められるため、家族の負担が軽減できる。
▶ 生前整理は何から始めるのか
生前整理には、持ち物の整理・財産の棚卸し・遺言書の作成・エンディングノートの活用など、項目ごとに始める内容が異なります。
以下、詳細です。
1.持ち物の整理
大まかに整理するのではなく、「要るもの」「要らないもの」「人に譲りたいもの」に分類し、整理しましょう。
その他にも、リサイクルや寄付、売却などを活用もおすすめです。自分にとっては不要なものでも、見知らぬ第三者が必要なこともあります。
2.財産の棚卸し
現在の財産を棚卸ししてみましょう。
- 預貯金
- 不動産
- 保険
- 借入金 など
項目ごとにリスト化することで、現在所有している財産を改めて把握できるだけでなく、今後、財産をどのように運用したいのか明確にできます。
3.遺言書の作成
あなたの死後、財産分割でのトラブルを防ぐために遺言書があると安心です。
特に、内容の不備で無効になるおそれがほとんどない公正証書遺言の作成検討をおすすめします。
4.エンディングノートの活用
自分の希望をエンディングノートに記録しましょう。
- 医療(延命措置の有無 など)
- 葬儀(葬儀社・葬儀の規模・葬儀の内容 など)
- 相続(遺産分配・寄付の希望 など)
- デジタル遺品(スマホ、サブスク、ネットバンクなどのIDやパスワード)
▶ 生前整理で費用を抑えるには
生前整理を進めることで、あなたの死後に行われる遺品整理費用や相続時の負担を大幅に軽減することができます。
以下、費用を抑える方法です。
1.遺品整理の業者費用削減
生前整理を進めておくことで、「遺品整理」の費用を負担できます。こちらは、上記のメリットにも該当します。
生前整理を行わず、遺品整理業者に依頼した場合の相場は以下の通りです。
- 1R・1Kなど少量の場合:約3万円~8万円。
- 2LDK:約15万円~30万円。
- 一軒家:家屋の規模によって異なりますが、50万以上かかることも。
*事前に不要なものを処分しておくことで、遺品整理にかかる費用が抑えられます。
2.相続税や財産管理のコスト軽減
生前に相続に対し、準備することで、相続税や財産管理にかかる費用を抑えることができます。
1⃣相続税についての対策
相続税は、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に発生するものです。これを軽減する方法として、以下の対策があります。
[生前贈与の活用]
基礎控除の範囲内で年間110万円までは非課税です。
但し、2024年の税制改正により、過去7年分の贈与が相続財産に加算されるようになりました。生前贈与を検討される際は、早めの行動がカギとなります。
毎年、同じ時期に同じ金額を贈与をしていると、定期贈与とみなされて贈与税が課税されてしまいますので、贈与をするときは贈与契約書を作っておくといいでしょう。
[住宅取得資金の贈与特例]
こちらの活用もおすすめです。但し、この制度には、注意点や適用期限があります。活用を検討される際は、しっかりと確認を行いましょう。
(*住宅取得資金‥親や祖父母から住宅購入のための資金をもらった場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度)
2⃣生命保険の活用
生命保険を活用する場合、「500万円×法定相続人の数」まで非課税になります。
相続財産を軽減しつつ、保険加入することで家族に現金を残すことができます。
相続財産が不動産メインの場合、他の相続人への代償費用に充てることができます。
▶ まとめ
終活と聞くと暗い印象に捉えがちの生前整理。進めるのであれば、早めをおすすめします。
生前に整理することは、あなたの意志を大切な人に託すことにも繋がります。
もし、相続で希望することがあり、あなたが元気なうちに叶えられることがあれば、早めに行動に移しておきましょう。
その中で、生前贈与などの専門的な知識が必要な場合は、専門家への相談をおすすめします。
「財産整理の目録を検討している」「遺言書の作成に悩んでいる」など、行政書士にご依頼可能です。
種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。
大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。