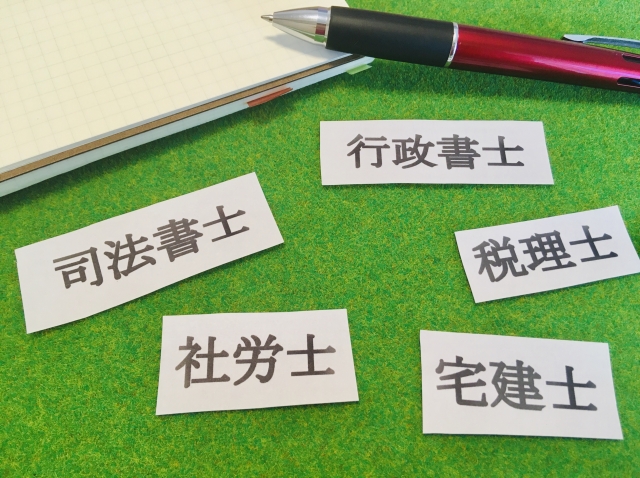
年金の相談をしようと思ったら、行政書士より社会保険労務士へ、税金の相談は税理士へ、土地の売却は司法書士へと言われましたが、まとめてできないのでしょうか。各士業の独占業務も教えてください。
「年金の相談をしようと思ったら、行政書士より社会保険労務士に相談、税金のことは税理士、土地の登記は司法書士にと言われてしまい、結局誰にどう相談したらいいのかわからない…」といったお声をいただくことも。
「○○士」と呼ばれる専門職の士業は、独占業務と呼ばれる専門分野を持っており、他の士業が代わりに行うことが法律で禁じられている業務もあります。
では、どの士業がどの業務の専門なのか、まとめて相談できる窓口はないの?など、疑問点はいくつもあるのではないでしょうか。
そこで今回は「相談窓口がバラバラ…?士業ごとの役割と“まとめて相談”の方法」についてご紹介します。
▶ 士業とは?
名前に「○○士」がつく国家資格を有する専門職の総称を指します。
読み方:しぎょう
例えば、
- 弁護士
- 税理士
- 司法書士
- 行政書士
- 社会保険労務士(社労士)
- 公認会計士
- 弁理士 など
これらの職業は、特定の法律に基づいて独占業務(その士業でしかできない業務)を持っており、専門知識を活かして書類作成や相談、手続きなどを代理で行います。
▶ 士業の特徴
特徴は以下の通りです。
- 国家資格が必要
- 法律で守られた業務範囲が存在する
- 業務の独占性がある(他の人が代わりに行うと違法になる場合がある)
- 個人や企業からの法律・手続き面での支援を行う専門職である
▶ 各士業の「独占業務」とは?
法律でその士業だけが行うことができる業務のことを指します。
以下、各士業ごとの独占業務です。(※一部士業の業務を抜粋)
【行政書士】
- 官公署(市役所・各省庁・警察など)に提出する書類の作成・提出の代理
- 各種契約書や遺言書、内容証明の作成など(※ただし、裁判や税務・登記・社会保険の手続きなどは業務の対象外)
- 行政に対する不服申し立ての手続きの代理(特定行政書士のみ、現在は行政書士の関与したもののみですが、令和8年1月1日より改正行政書士法により行政書士が関与していない場合にも不服申し立ての代理人になることができるようになります)
【社会保険労務士(社労士)】
- 年金・労務保険(雇用保険・労働保険)の申請手続き(※年金請求の代行は社労士の独占業務です)
- 就業規則の作成や労務相談
【税理士】
- 税務申告・税務代理(確定申告や相続税申告など)
- 税務相談(税金に関する具体的なアドバイス)
※無資格者や他士業が有償で税務相談を行うことは違法行為です。
【司法書士】
- 不動産登記(所有権移転登記など)
- 法人登記(会社設立登記など)
- 一定額までの簡易裁判所の代理業務(※認定司法書士のみに認められる)
▶ 相談はまとめてできない?
士業ごとにできる業務は異なるため、「全ての対応」を求めるには難しいのが現実です。
ですが、「士業同士の連携」によって、複数の相談を一ヶ所でまとめて受けられることもあります。
例えば)
1.初めの窓口として行政書士に相談する
2-1.年金の話しが出た場合:信頼できる社労士を紹介してもらう
2-2.土地売却の話しになった場合:司法書士や不動産会社と連携することも
行政書士は「法務の総合窓口」としても多くの役割を担っていることがあります。
- どの士業に相談したらいいのかわからない
- 相続や遺言の手続きや内容証明などの書類作成が必要
- 許認可(建設業/飲食業/介護事業など)を取得したい
- 外国人の在留資格やビザの手続き など
これらに該当する際は、まずは行政書士へ相談することで、相談に対して適切な士業へ繋げることが可能です。
▶ まとめ
各士業には専門知識を活かして書類作成や相談、手続きなどを代理で行う、独占業務があります。
独占業務を無資格者や他士業が有償で請け負ってしまうと法律に違反するため、相談をまとめて解決していくことが難しいのが現実です。
しかし、「法務の総合窓口」である行政書士に相談することで、必要な手続きや専門家との連携がスムーズになるでしょう。
さまざまなご相談もお持ちの方は、まずは行政書士にご相談ください。
種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。
大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。











